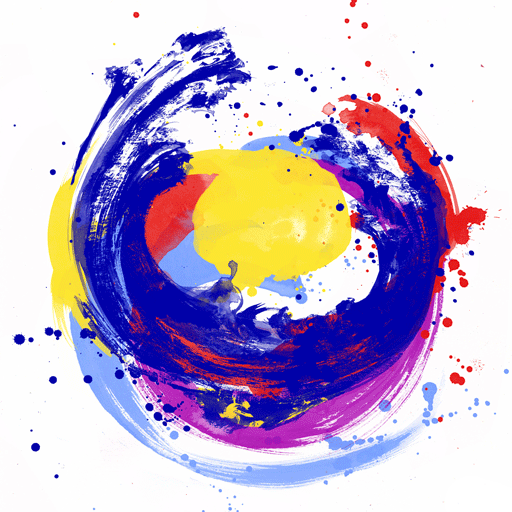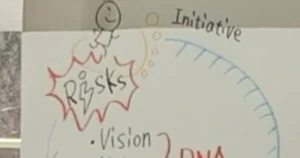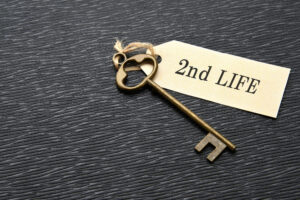先日、構造、ロバートフリッツのコンテンツを国内で提供するお二人と会食してきました。
ロバート・フリッツ・コンサルティング
このロバート・フリッツの構造思考もさることながら、1番私が興味を惹かれたのはピクチャリングという技法。
これは言語化と対になるというか、
情報、状況を言葉に変換せず映像として思い描く技法
です。
私のポリシーの一つとして、
物事をありのままに見る、偏見のない完全な世界に生きる
というのがあります。
このピクチャリングはその助けになるように感じたんですよね。
(言語化の過程でその人の価値観、偏見などバイアスがかかる)
そしてその席での中心となったテーマが
深く考える
ということ。
「?」
…となるかもしれません。

わたしも含めて人は深く考えることを深く考える機会があまりないと思います。
自分は日頃、物事に対してどこまで深く考えられているのか?
これはあまり意識しないことかもしれません。
思考の深度が人生の深度に比例し、またそれが人としての器の大きさに繋がると考えています。
(ただし思考の浅深は善し悪しでなく嗜好、後述するウェルススペクトルの「生き方を選ぶ」と同様)
この席では物事を深く考えられるかどうかは人それぞれだよね、
そしてこれはトレーニングでもある、というような内容でした。
これには強く同意します。
ウェルススペクトルは人の意識レベル、興味、関心、社会的役割、立場などを表す指標です。
このウェルススペクトルのレベルが高いほど思考の深度が深いと言えるかもしれません。
それは、高いレベルで要求される課題を認識する上で思考の深さを要求されるからです。

高いレベルで生じる課題、物事を認識するために深く考える必要が出てくる。
物事の認識、理解、解釈、その解像度の高さは思考の深度に比例します。
これは状況をありのままに正対し捉え、それに対応していく経営者にとって重要な要素です。
解像度が低いとマネジメント、経営戦略の程度も曖昧、ぼやけたものになってしまいます。
スペクトルレベルを上げる選択をした時、自分が物事をどれだけ深く考えられるかも要求されます。
様々思考技法、理論がある中、今回のロバート・フリッツが提唱するピクチャリングもその助けになるかもしれないと思いました。